Scienceサイエンス
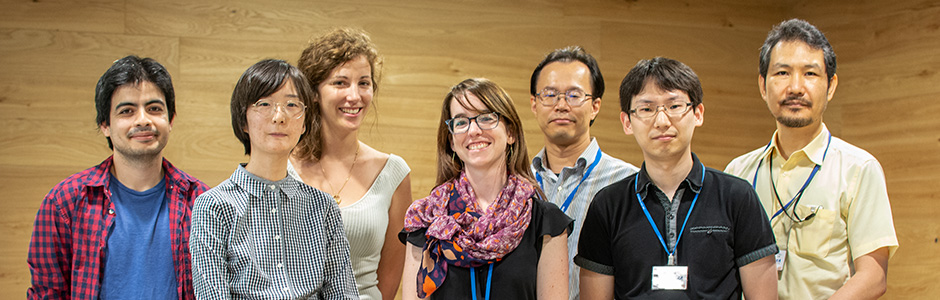
MMXミッション目的を達成するため、11の科学ミッション機器が搭載されます。
MMXを世界最高のミッションとするため、そのうちの4つは海外機関から提供されます。
加えて、探査技術獲得を目的とする2つの機器を搭載します。
Remote Sensing and In-Situ Observationリモセン・その場観測
MMXはサンプルを採取するだけでなく、様々な観測機器によって火星衛星や火星のリモートセンシングも行います。
2つの小さな衛星がどのように形成され、どのような過程を経て現在の姿になったのかは、まだ謎に包まれています。
可視・近赤外光で見た火星衛星表面は均一でなく、構成する物質が異なる可能性も考えられています。
どの場所からサンプルを取るべきなのか、国内外の科学者によって議論が進められており、リモートセンシングで得られるデータも使ってサンプル採取地点が決められます。
TENGOO / OROCHI
TENGOO
衛星表面の詳細地形を観測するための望遠鏡です。約40cmの解像度で地形を撮像し、物質分布や回収サンプルとの対応の情報を得るほか、着陸地点の安全性確認にも利用されます。
OROCHI
衛星表面の地形、物質情報を観測するためのカメラです。衛星表面からの可視反射光を多波長で撮像し、全球およびサンプル採取地点周辺における含水鉱物・有機物などを計測します。

亀田 真吾Shingo Kameda
立教大学 教授
専門分野:惑星物理学
私はこれまで小惑星探査機はやぶさ2や水星探査機みおに搭載されたカメラの開発を行ってきました。MMXのカメラは、これらの太陽系探査での開発経験を活かし、最適・最高性能のものとして完成させたいと考えています。
LIDAR
衛星表面の形状情報を観測するための測距装置です。
レーザを衛星に向かって射出して、反射光が返ってくるまでの時間と、反射光のエネルギーを計測することで、表面の高度やアルベドの分布を導出します。

千秋 博紀Hiroki Senshu
千葉工業大学 主席研究員
レーザ高度計は、時々刻々と変化する探査機の高度を測り続けます。
得られるデータは数字の羅列で、カメラ画像のような華やかさはありませんが、長い期間にわたって、高い精度で取得するデータ
ならではの面白さがあります。この面白さはどうすれば多くの人に届けられるのか、日々頭を悩ませています。
MIRS
MMX InfraRed Spectrometer (MIRS) は火星の衛星を構成する鉱物の特徴を明らかにするための近赤外線観測装置です。
MIRSは、0.9~3.6ミクロンの波長帯の近赤外光での分光観測により、火星衛星地表全体の含水鉱物、水関連物質、有機物の分布を測定し、サンプリング場所の選定に活用される予定です。
MIRSはフランスの宇宙機関であるCentre National d'Etudes Spatiales (CNES)と連携して、LESIA-Parisを中心としたフランスの他の4つの研究所(LAB, LATMOS, LAM, IRAP-OMP)と共同で開発されています。

マリア・アントネッラ・バルッチMaria Antonietta Barucci
パリ天文台 天体物理学空間計測研究室、教授
これまで、カッシーニ・ホイヘンス、ロゼッタ、ベピコロンボ、OSIRIS-REx、はやぶさ2に深く関わってきました。今回MMXに参加し、このエキサイティングなミッションに近赤外線分光装置MIRSで貢献できることを特に誇りに思います。 MIRSは、フォボスとダイモスに存在する鉱物や有機化合物を検出し、その性質や起源を理解することに貢献します。また、MIRSは火星環境の進化の過程も調査する予定です。 私の挑戦は、未知のものを知らしめることです。
MEGANE
MEGANEとは、「Mars-moon Exploration with GAmma rays and NEutrons」の略です。
これは、フォボスを構成する化学元素を測定するガンマ線・中性子線分光装置です。MEGANEが検出するガンマ線と中性子線は、フォボスの表面に絶えず降り注ぐ宇宙線と、表面の岩石に含まれる天然放射能から発生します。MEGANEの組成測定は、フォボスの起源を決定し、フォボス表面が経た過程を研究し、MMX探査機によるサンプル収集地点の選択を支援し、サンプルに重要な背景を与えるため、重要な情報を提供するものです。
MEGANEは、NASAアメリカ航空宇宙局とのパートナーシップにより開発されています。

デイビッド・J・ローレンスDavid J. Lawrence
ジョンズホプキンス大学 応用物理学研究所、惑星科学者
MEGANEチームは、MMXミッションに参加し、ガンマ線・中性子惑星分光の経験を活かして、火星の衛星フォボスに関する魅力的な疑問の理解に貢献できることを大変嬉しく思っています。 このエキサイティングなミッションで、技術者や科学者の同僚と一緒に仕事を続けることを楽しみにしています。
CMDM
衛星周辺のダスト環境を明らかにするための装置です。
大きさ10μm以上のダスト存在量を計測し、ダストを生成する天体衝突頻度や、衛星へのダスト再集積現象について調査します。

小林 正規Masanori Kobayashi
千葉工業大学 主席研究員
専門分野:惑星探査
MMXミッションに参加することができ、大変うれしく思っています。長年に亘って理論的に予想されながらまだ見つかっていない火星周回ダストの発見を目指しています。装置開発、軌道上運用、データ解析と先は長いですが、精一杯頑張りたいと思います。
MSA
衛星周辺のイオン環境を明らかにするための装置です。
衛星から放出されるイオン、火星から放出されるイオン、および太陽風イオンを計測して、衛星内部の氷の存在、衛星表面の風化作用、火星大気散逸量などを調査します。

横田 勝一郎Shoichiro Yokota
大阪大学 准教授
専門分野:惑星物理学 多くの方のご尽力のもとで、MSAチームとしてMMXプロジェクトに参加できる機会が得られました。 これまで私たちは地球や水星周辺で荷電粒子や磁場の観測を行ってきました。 今後新たに火星やフォボス周辺で観測が実施できるように、準備に努めていきます。
Rover
火星衛星探査機本体より先に着地し、母船着陸・サンプル採取運用リスク低減のための表層レゴリスの各種物性取得、
およびサイエンス観測の校正データ取得等を目的とするフォボス表面探査を行います。
フランス国立宇宙研究センター(CNES)とドイツ航空宇宙センター (DLR) との共同開発です。

ステファン・マリーStéphane Mary
CNES ローバプロジェクト責任者
MMXローバーをフォボスに届けるという、驚くべきMMXミッションに参加できることを大変誇りに思います。フォボスまでは長い道のりですが、フォボス表面でも長い道のりを歩めるように最善を尽くします。ローバーが収集したデータが、科学者がフォボスのレゴリスの組成や機械的特性を分析するのに役立つことを期待しています。
Sampling and Returnサンプル採取・回収
MMXのサンプル採取機構は2種類あります。また、回収カプセルがあります。
CSMP
火星衛星表面から深さ2cmに渡るまでのレゴリスを採取し、リターンカプセルに移送します。

加藤 裕基Hiroki Kato
JAXA 研究開発部門 主任研究開発員
専門分野:ロボティクス
ロボティクスの専門家である私は、ロボティクスミッションが自由に宇宙に打ちあがっていく未来を目指しています。そして、MMXのサンプリング装置は歴史を一つ刻み、世界に誇れるステップです。MMXが火星圏に行ってサンプルリターンに成功すれば、有人火星探査の話もどんどん出てくる、つまり人類の進歩への貢献を感じられるのです。MMXで世界初の火星圏サンプルリターンを成功させます。
P-SMP
P(空気圧)サンプラーは、火星衛星の表面から加圧ガスを使用して物質を巻き上げて、 一瞬でサンプル容器に格納します。NASAが提供するPサンプラーは、Honeybee Robotics社が製作しています。

クリス・ザクニKris Zacny
Vice President of Exploration Systems Division at Honeybee Robotics
専門分野:宇宙採掘・掘削、サンプル採取・ハンドリング、その場資源利用(ISRU)
MMXミッションに参加し、人類史上初めてフォボスと火星のサンプルを持ち帰るお手伝いができることを大変嬉しく思っています。
空気圧を使った採掘技術は20年以上前から開発してきました。NASAとJAXAが私達の技術を採用してくれたことは非常に幸運なことです。
頑張れMMX!
SRC
サンプリング装置によって得られた火星衛星表層サンプルを地球へ持ち帰ります。

鈴木 俊之Toshiyuki Suzuki
宇宙科学研究所 研究領域主幹
専門分野:熱防御技術,空気力学 MMXミッションに参加することができ、大変誇りに思っています。 貴重な火星衛星表層サンプルを安全に確実に地球に持って帰ることができるように精一杯頑張ります。
Exploration Technology Acquisition探査技術獲得
将来の探査技術を獲得する目的で、MMX飛翔機会を利用して2つの機器を搭載します。
IREM
太陽高エネルギー粒子のエネルギースペクトルを取得し,被ばく線量評価手法を確立します。

宮崎 英治Eiji Miyazaki
JAXA研究開発部門 第一研究ユニット 宇宙環境・材料領域 研究領域主幹
専門:宇宙材料学
将来の宇宙探査の発展に貢献できるよう、取り組んでいきます。
SHV
高精細な火星衛星の撮影およびミッション可視化を行い,宇宙探査の運用性向上およびアウトリーチに貢献する技術を獲得します。

船津 良平Ryohei Funatsu
日本放送協会技術局 エキスパート
専門分野:放送用カメラ
MMXミッションに参加させていただき、NHKの8K・4Kカメラを搭載させていただけることを大変うれしく思います。まだ誰も見たことのない、超高精細な火星圏の映像をみなさまにお届けできるよう、カメラ開発に取り組みます。
